
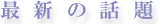
(2008年5月26日更新)
これまでの話題はこちら
●聟島のアホウドリ 1羽が巣立ちました!
小笠原諸島聟島で飼育中のアホウドリ10羽のうち、メス1羽が5月19日8時20分ごろ巣立ちしました。この個体は、最も早く自然繁殖下の巣立ち体重に近づいた個体で、最近は頻繁に羽ばたき練習を行っていました(2008年5月19日更新)。 |
|
|
| |
●聟島のアホウドリ 順調に発育
2月19日に伊豆諸島鳥島から小笠原諸島聟島に移送され、人工飼育中の10羽のアホウドリのヒナは順調に発育しています。移送の翌日から、スルメイカやトビウオのミンチ、ビタミン剤等の給餌を受け、移送直前の平均体重約4.3キログラムから、4月19日には平均体重が約6.4キログラムに成長しました。現在ではミンチにしないトビウオやスルメイカ等も給餌しています。これから徐々に絶食して体重を軽くし、1ヶ月前後で巣立ちを迎える見通しです(2008年5月2日更新)。
>移送当初のニュース
小笠原諸島への再導入の背景については、「アホウドリ復活への展望 小笠原諸島への再導入へ」をご覧ください。
|
 綿羽に代わって真羽が生え始めたヒナたち(4月28日撮影)
綿羽に代わって真羽が生え始めたヒナたち(4月28日撮影)
|
●「日本産鳥類資料の整備と活用に関する研究」
科学研究費成果発表会を開催 〜象鳥(エピオルニス)研究を特集〜
山階鳥研では、2008年2月6日に、文部科学省科学研究費補助金を受けた「日本産鳥類資料の整備と活用に関する研究」の平成19年度の研究成果発表会を、また翌7日には研究調整会議を行いました。二つの催しには、総裁の秋篠宮殿下が臨席されました。
本年度の研究発表会は、第一班「標本資料および組織サンプルの収集・整備・活用」のうち、秋篠宮殿下が研究班の総合統括を務められる「絶滅鳥エピオルニス(象鳥)の総合的研究」の成果を特集する形で行われました。我孫子市内の千葉県手賀沼親水広場「水の館」で、所員のほか、外部評価委員、客員研究員、共同研究者ほかの方々の参加を得て開催されました。
研究調整会議は山階鳥研にて開催し、外部評価委員の方々に、現在の研究の問題点や今後の方向づけについて討議をお願いしました。
(山階鳥研NEWS 2008年5月号より)
|
 エピオルニスの骨格標本レプリカ
エピオルニスの骨格標本レプリカ
(進化生物学研究所蔵・「鳥のビオソフィア展」から)
|
●第一回九州地区賛助会員の集い
2008年2月12日、エルセルモ熊本(熊本市)で「九州地区賛助会員の集い」を開催しました。総裁秋篠宮殿下のご臨席を仰ぎ、多くの新入会員を含めた、およそ200名の皆様にお集まりいただいて、なごやかな親睦のひとときを過ごしました。
まず、九州地区世話人代表の安田征史様から、九州地区が西日本地区から独立して賛助会員の集いを開催するに至った経緯等についてご説明があり、次に、熊本県知事(当時)の潮谷義子様よりご祝辞を頂戴しました。
引き続き、秋篠宮殿下から高額寄附者の安田征史様に感謝状を贈呈し、また、島津理事長が九州地区の初の集いの開催にあたりご尽力いただいた関係者の皆様への御礼の言葉を述べ、末永いご支援をお願いしました。
そのあと、山岸所長が山階鳥研の活動の概要をスライドによりご説明し、引き続き懇親会を行いました。
(山階鳥研NEWS 2008年5月号より)
|

乾杯風景(前列左から、秋篠宮殿下、
世話人代表の安田征史様、島津理事長、
山岸所長) |

九州地区の集いのためにご尽力いただいた、左から二宮義人様、小野勇一様、古葉竹識様
|
|
「山階鳥研NEWS」は山階鳥研の活動や鳥の話題を紹介した隔月刊行のニュースレターです。賛助会員にご入会いただいた方にお送りいたします。(賛助会員の入会はこちら)
最新号の目次はトップページをご覧ください。
|
トップページ|これまでの話題
Copyright 2002, Yamashina Institute for Ornithology. All rights reserved.







